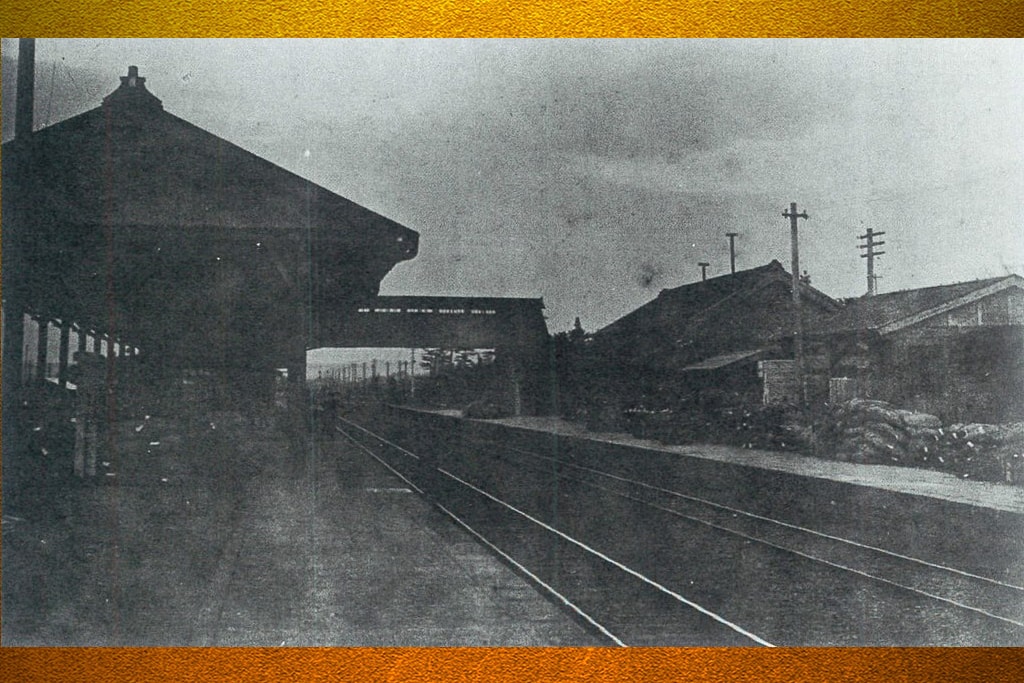今ではひとつの街に必ずと言っていいほどあるパン屋。
雑誌でパンの特集が度々組まれるなど、すっかり日本に根付いています。
どのパン屋が美味しいか話題になったり、朝にはご飯ではなく、パンを食べる人が多くなるなど、これからも人気がましていきそうなパン業界。
昔はすべて手ごねで作っていたため、現在よりもずっと重労働だったパン屋の仕事ですが、次第に機械化が進み、随分様変わりしました。
そんなパン屋の作業の機械化が進んだのは大正時代。
では、当時のパン屋を取り巻く状況はどんなものだったのでしょうか。
男手不足で機械化?
大正時代にパン屋の仕事の機械化が進んだことを説明する為には、まず当時の海外の状況を知ることが大切になってきます。
パン屋の仕事の機械化が進んだ原因は海外の国にあるためです。
まず先に機械化が進んだのは海外の国から、そして機械化が進んだきっかけは第一次世界大戦でした。
この戦いにより、海外では男手不足が深刻になっていきます。
そしてその影響はパン屋にも及びました。
パンをこねるなど、作るために力のいるパン屋は男手が必要不可欠。
しかし、男手が不足してしまったため、ヨーロッパでは自動こね機が普及するなど、パン屋の仕事の機械化が進んだのです。
パン工場は機械化され、ガスオーブンや電気オーブンも登場し、それらが一気にそれまでのパン屋を変えていきました。
パン業界を変えたイースト
世界のパン屋で進んだ仕事の機械化の波は日本にもやってきます。
第一次世界大戦が日本のパンに与えた影響はそれだけではありません。
その戦いで捕虜になったドイツ人が日本でドイツパンを焼き、そのために必要なドイツ式の釜を各地の収容所で作るなども日本のパン業界を変える出来事でした。
また、パン生地を膨らますのにかかせないイーストもアメリカから輸入され、パン屋に大きな変化を起こします。
明治から大正時代、そして昭和初期にかけて、日本でイーストが普及するまではホップ種という発酵種が一般に使われていましたが、1913年、国産イーストが開発されるなどしたため、主流はイーストに移っていきます。
イーストの魅力はその手軽さと安定感。
それらを手に入れた日本のパンは、それまで主流だったパンを大きく変えていくのです。
大人気パン、誕生
明治時代には、現在の日本のパン屋でもお馴染みのアンパンやクリームパンが日本人の手によって作り出され、定着していきました。
イーストが輸入され、国産のイーストも作り出されるようになったこと、そして、パン屋の仕事の機械化が進んだこと。
それらの要素が合わさり、大正時代は日本のパン屋の近代化が進んだ時代でした。
それまではヨーロッパ風の、水と小麦粉だけで作るようなパンが日本の主流でしたが、徐々に砂糖やバターがたっぷりのアメリカ風のパンやバターロールが主流となっていくのです。
様々なパンが生み出された明治時代、そしてさらに発展していく大正時代。
現代のパンにつながるパン屋の環境が大正時代には整っていったのです。